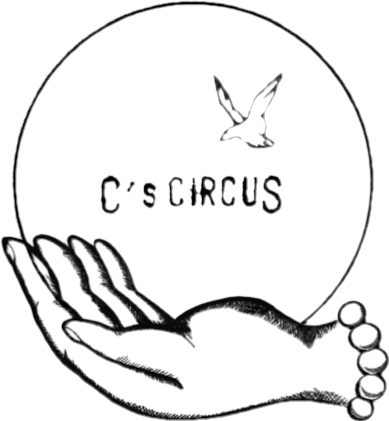2021/01/31 11:09

こんにちは。
ついこの間、年が明けたと思ったら
あっという間に1月が終わり、まもなく節分・立春を迎えます。
月日が経つのが早いですね。
節分と言えば、これまでほぼ毎年2月3日でしたが、今年は例年より1日前倒しで2月2日です。
節分とは『立春の前の日』の行事であり、今年の立春は2月3日のため、節分もずれてしまったというわけです。
実は節分・立春がずれるというこの現象、驚くことに124年ぶりとのことです。

◆立春を決めてるのは国立天文台
毎年の暦を計算して、立春を発表するのは国立天文台の役割だそうです。
毎年2月に翌年の暦要項を発表しているそうです。
カレンダーに書かれている二十四節気や祝日や月の満ち欠けなども、国立天文台が計測しているそうです。
これまでほぼ毎年、節分の日は2月3日で固定的でしたが、2月2日になるのは124年ぶり、明治30年代以来とのことです。
その後に昭和59年に2月4日になるという年があり、3日でない節分は37年ぶりのことだそうです。
日付の変動がおこるのは、地球の公転周期が約365.2422日であって、いわゆる1年間の365日から0.2422日分、微妙にズレているために生じてしまうとのことです。
昨年末に木星と土星が水瓶座に移動し、風の時代に移行したのは240年ぶりとのこと。
この頃、立て続けに天体の動きによる変化に遭遇していますよね。
たまたまこの時代に生まれてきた私たちは、単なる偶然ではないのかも知れませんね。
では次に立春ではじまる二十四節気の暦についてです。
◆二十四節気の分け方
立春とは、1年間を太陽の動きに合わせて24等分した「二十四節気」のうちの一つです。
はじめは農作物を育てるための目安として作成されたようですが、今では暦の上での季節感と季節を味わう行事の一部としてとらえられています。
分ける数え方は「二至」「二分」「四立」「八節」です。
順に説明しますね。
まず、一年を春夏秋冬に分けます。
ざっくり夏と冬に分け「二至」で夏至と冬至
さらに春と秋に分け「二分」で春分と秋文
ここまででだいたい4つに分かれました。
それぞれは3か月(約90日)です。
今度は春夏秋冬それぞれの中間に節で区切って
「八節」、立春・立夏・立秋・立冬。
それぞれは約45日ずつになります。
この45日を三等分にすると8×3で24、それぞれが約15日ずつで二十四節気となります。
じつはまだ続きがあるんです。
この12日を5日ずつ三等分します。
24×3で72、七十二侯の時候にまで細分化されます。
カレンダーに書いてある時候はこういう分け方をしていたというわけです。
日本の暦って面白いですね。
◆1年の始まりは立春から
旧暦では一年のはじまりは立春からと考えられていました。
いまでも立春を旧正月といい、この日を基準にして様々な行事があります。
立春の前日、季節の暦ではこの日が大晦日に当たります。
一年の厄払いをし、運気を呼び込むために『鬼は外、福は内』といって豆を撒きます。
暦の上での春は立春から3か月間、立夏の前日までを言います。
♪夏も近づく八十八夜、野にも山にも若葉が茂る♪
「茶摘み」という有名な歌があります。
旧暦の夏は立春から約90日後ですので5月の初め、ちょうど若葉の頃ですね。
この日に摘んだお茶は霜がかぶらないので、美味しくて高級なお茶になると言われています。
こんなふうに、立春から数えて何日め頃に季節の変化を感じることができるよ、という五感を感じることのできるというのが、旧暦なんですね。
ちなみに、立春の早朝に「立春大吉」と書いて門に貼っておくと厄払いになるそうです。
「立春大吉」は縦書きにすると左右対称になるそうで、左右対称は災厄に遭わなくなるおまじないの効果があるそうです。
そう言われてみれば、日本に限らずお寺や神殿の入り口にはたいてい左右対称の何かがありますね。
あれは、おまじないの意味があったんですね。
ちなみに、立春以降に初めて吹く強烈な南風を「春一番〔はるいちばん〕」と呼ぶのだそうです。
まだまだ寒い日が続きますが、暦の上ではもう『春』そして、旧暦で言うところの『新年』
時代も土から風に移り変わったところですし、
いろいろな意味で、生まれ変わった気持ちで心機一転、自分を甘やかして盛り立ててあげてくださいね。